くわさん✨️のプロフィール
はじめまして!くわさん✨️です。
ボクは現在、神奈川県秦野市を拠点としてスポーツや教育の現場の伴走をしたり、笑顔あふれるコミュニティをつくりたい人たちに向けてボトムアップ×しつもんで講演や研修、ワークショップをしています。
また、「人生という名のボールは転がり続ける」をモットーに「一度しかない人生を自分らしく生きてみたい!」という人たちに向けてパーソナルコーチングも。
2023年9月からは「ともに歩もう、この先の秦野へ」を掲げ秦野市議会議員としても活動を始めました。

もともと何の変哲もない普通の体育会系小学校教諭でしたが、教育委員会への出向をキッカケにブログを始めて20年以上が経過しました。
ブログが流行り始めた頃からドメインを取得してレンタルサーバーにMovable TypeやNetCommonsなど数々のCMSを突っ込んではあれこれと試して現在のWordpressによる運用に至ります。
子どもたちの日頃の学校生活をできる限りリアルタイムで伝えていくために学校ウェブサイトを作ったり、市内小中学校のプラットフォームを作ったりもしました。
「まずはやってみる!」ことを大切にしながら、デスクトップパソコンを自作したり、ノートバソコンを分解して修理したりと「あーでもない!こーでもない!」を繰り返すような毎日が楽しくてしょうがありませんでした。
スポーツの現場では、3人の子どもたちが小学生になったことに合わせてサッカーコーチとしての活動を20年近く。
日本サッカー協会の公認指導者ライセンスも取得して、平日は学校の子どもたち、土日はサッカーの子どもたちと過ごすようになりました。
学校と地域スポーツの両面を見つめながら、中心にいる子どもたちがすくすくと育つ環境づくりを真面目に考えるようになり、2008年にJFA Sports Managers College本講座を受講したことがキッカケとなり2010年には大学院へも進学。
この体験によって物事の見方が劇的に変わって学校や地域スポーツを支えるための多角的な視点を持つことができるようになりました。
何かをつくるのではなく、そこにいる子どもたちや大人たちが元気になる場をつくるために生命力あふれる土壌を準備し、必要があれば清らかな水をそっと引いてくるような環境設定を考える日々が続きます。
2012年の夏、オランダへ渡りロッテルダムでサッカーを観戦したり、イエナプラン教育の研修を受けて帰国。
この何とも刺激的な一週間の体験が、スポーツと教育の現場に横串を刺し、「一人ひとりの物語を大切に!」というマインドセットを築き上げてくれました。
帰国後、「誰かと比較するのではなく、人それぞれ自分らしく生きることができる世界をつくりたい!」と考えて公立小学校の教室にサークルベンチを置きました。それまでの教師主導型の学級づくりから子どもたちと対話しながら成長する学級への転換を図ったのです。
正直に言うと子どもたちに委ねる不安と、批判にさらされる恐怖の中があり、とても苦しいものでしたが、子どもたちや保護者の皆さん、勤務校の先生たちや全国の仲間たちと理想の教室を追いかけた7年間の体験は今でも大きな財産となっています。
「一人ひとりの物語を大切にした教室をどのようにつくるのか?」という命題で子どもたちと向き合った記録は数え切れないほどのブログ記事となり、それまでの活動のご縁によって閉校した学校に私立小学校をつくるというプロジェクトにも参画。2020年には書籍としても読んでもらえるようになりました。
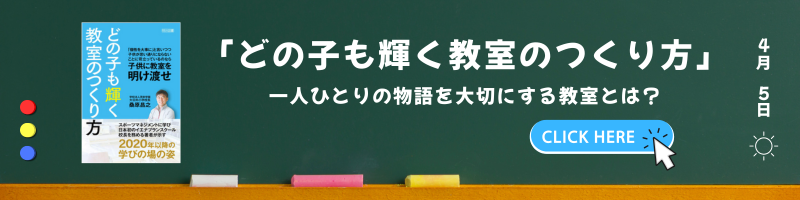
こんな感じで紹介すると、一見順風満帆に見えるかもしれませんが、
その裏では「批判や中傷」「自分の想いと行動のギャップによる葛藤」「結果ばかりを気にする毎日」など、決して安泰とはいえない苦悩もありました。
ここからは、生い立ちや今までの活動を振り返りながら、どんな信念を持って生きているのかを紹介します。
スポーツと教育の現場への道

小さな頃から身体は大きめなれど、足も遅く、高く跳ぶこともできない普通の少年でしたが、ボール遊びが大好きで小学校4年生からサッカーを始めました。
1970年代と言えば野球全盛の時代なのにボクらは大根(おおね)ラディッシュでサッカーばかりやっていて、何だか分からないうちに県内でも強豪チームとして知られるようになりました。
ボクらをサッカーの道へ引きずり込んだ監督は「くわ!お前の得意なプレーはなんだ?」と常に問いかける小学校の先生でした。
おかげでサッカーが大好きになったボクは小学校6年生時に104ゴールとチーム内得点王でした。まあ、周りにいる仲間がゴール前に走り込むボクに最高のボールを渡してくれただけなんですけどね。
「くわさん!スポーツの中で何がいちばん大好きですか?」って聞かれたら、「そりゃあサッカーでしょ!」と即答。
なのに…
中学校から大学までバレーボール部に所属してバリバリの体育会系となりました。高校時代は当時は珍しい自分たちで考えるスタイルで仲間にも恵まれ関東大会にも出場。身長はプログラム上は180cm(実際は179cm)で大して跳べないサイドアタッカーでしたが頑張りました。
そんなボクが「将来は学校の先生になろうかなあ?」という思いを抱いたのも高校時代です。熱中時代、金八先生、スクールウォーズの時代でもあり、小中高の先生たちとの出会いが良かったのもあります。
そんなわけで体育系の学部や学科がありバレーボール雑誌に名前が登場する大学を探し始めました。「私立に行かせる金はないよ!」というので一年目は東北リーグ1部だった福島大学を受験するも失敗。予備校へ行かせたい父とのバトルを制して宅浪で一年間なんとか頑張って関東リーグ3部(現在の2部)だった東京学芸大学へ入学。大学バレー界では小さいけれど元気な声を張り上げて4年間コートを走り回らせてもらいました。「お前、声だけでレギュラーだったよな」というのも伝説の一部。
「さあ!いよいよ!学校の先生になるぞ!」と意気込んで臨んだ採用試験には見事に不合格。落胆していたボクに母校である秦野高校から非常勤講師の話が舞い込みます。そこで魂に火が付いてしまい小学校教諭よりも難関と言われる高校(保健体育)を受験するもまたしても不合格。
「もうどうしようもない!」と思っていたボクに「ちょっと校長室へ来なさい!」と体育大出身の校長先生から声がかかります。ドキドキしながらソファーに座ると「来年は小学校を受けて、合格して数年経ったら高校に転任希望を出しなさい」と諭されて騙されたかのよう再び勉強して翌年3回目にして合格。
やっと憧れの教壇に立ったけれども…
1992年(平成4年)に新採用となり4年生の担任となりました。
体育会系のボクは元気に子どもたちと休み時間に遊ぶことばかりで、肝心の授業は「???」とベテランの先生たちとの差に愕然とさせられる毎日でした。
当時は「分かる授業」というキーワードのもとで様々な授業方略が実践され、各教室で担任の実力が露わになって何だか辛い日々を送る状況が続きました。
不安を口にするボクに先輩たちは「大丈夫だよ!あなたにはみんなにない若さがあるんだからね!」と励ましの声をかけ続けてくれましたが、日に日に苦しさは増し続け、初めての転勤後の6年目に運命の一日が訪れます。
勤務校に行くには有料道路のT字路を左折しなければなりません。
ところが、何を思ったのか右にハンドルを切ってしまい、そのまま海辺へと向かってしまったのでした。
公衆電話から「途中まで来たのですが調子が悪いので休みます」と連絡をして夕方までグルグルと車で走り回って帰宅。
「明日は行くぞ!もう大丈夫!」と思って迎えた次の日も、その次の日も同じ事を繰り返すという状況に。
それからしばらく何をして過ごしていたのかは全く記憶がありませんが、唯一思い出すのは近所に住んでいるサッカーの恩師の車とすれ違ったこと。
「くわ!どうしたんだ!大丈夫か?」と同じ学校で働く教え子のボクを気遣ってくれたのです。
「お前な、真面目すぎるんだよ!休みたいときは休んでいいし、ムリならムリって言えばいいよ。みんなそうなんだからな」という言葉を聞いて少しずつ落ち着いてきたことを思い出します。
それからというもの「ちょっと今日は調子が悪いぞ。こんな日に学校にいっても満足に仕事はできない」と思う日は思い切って休みをもらうようになりました。
若かりし頃のボクは先輩たちにとっても厄介な存在だったのだろうと反省すると同時に、どんな時にも温かく見守ってくれたことに今でも感謝しています。
そのおかげで、少しずつ増えた後輩にも優しくできたのではないかと思ってもいます。
コーチや先生の仕事は子どもたちに何かを教え与えること?

3人の子どもたちが成長すると共に、いつしかサッカーコーチの道へと足を踏み入れるようになりました。
まだまだ、「コーチや先生の仕事は子どもたちに何かを教え与えること」を信じていた時代。
学校ではテストの成績を上げることに躍起になり、サッカーではチームの勝利こそが重要と信じて子どもたちの前に偉そうに君臨していたのです。
「あのさ!言ったよね。なんでやらない?ちゃんとやりなよ!」
子どもたちに言って聞かせて、こちらの意図を汲んで動いているかいないかで評価するような日々が続きます。
たしかにそれはそれで結果はバーッと出るので良かったとも思うのですが、その一方でボクの基準に満たない子たちには冷たい態度を取っていたこともあるのです。思い出すだけでも恥ずかしく、今でも当時の子どもたちには申し訳ない気持ちでいっぱいです。もちろん、この世に完璧な人間は存在しませんからコーチや先生たちも日々研鑽を積んでいることが大切だと頭では分かっていましたが。
「なかなかいいクラスですね」とか「強いチームですよね」と言われて自己満足に浸るだけの片隅で笑顔がない子どもたちの姿が目に留まるようになりました。
そう、ボク自身が誰かに「凄いね!」と言われたかったのであって、子どもたち一人ひとりの物語を大切になんていう心の余裕などはない。ボクの頭の中にあるクラスやチーム像を語っては子どもたちに強いていたのかもしれません。
しかし、それは大きな間違いだと気づくことになります。
我が家のサッカーボーイズたちにも個性があり、それぞれの歩み方が違うことも実感。サッカーの指導者講習会で頻繁に語られる「Player’s First」の影響もあり子どもたちとの関わり方を変えようと決心したのでした。
そして、もうひとつ。
38歳、2校目の任期を終えて伊勢原市教育センターの研修指導主事となりました。市内小中学校の先生たち450名の自主的な研修や研究、学校ICTや姉妹都市交流を支える仕事です。
それまで見たこともないような破天荒な先生たちとのふれあいもあり、個性の大切さを実感する4年間を過ごします。
先生たちが気持ちよく教育実践を進めていくための支援をすることが楽しくてたまりませんでしたが、苦しくて苦しくてどうしようもないこともありました。
時には校長会からお叱りを受けるとか、学校現場から苦情を呈されるなんてことは日常茶飯事。教育委員会内では「指導される主事」と言いながら励まし合いながら生きるしかなかったことも覚えています。
ただそこで大切なことも学びました。
当時の教育長から就任初日にいただいた言葉「権威は人のために使うんだよ!」という一言です。
今でも肝に銘じているこの言葉によって、それまでの価値観は粉砕されました。
「コーチや先生の仕事は子どもたちに何かを教え与えること?」と信じていたんですから…
すべては環境設定にあるのでは?

スポーツと教育の現場、さらには行政。
40代に入ると「場づくり」に目が向くようになります。もともとの専門分野であったスポーツコーチングの視点にマネジメントの視点が加わることになり学びを深めたくなりました。
そう思っている頃に大学の後輩から紹介されたのがJFA Sports Managers College本講座でした。
年間33日、JFAハウスを中心とした集合研修にE-ラーニングはハードでしたが、そこで学んだ分析手法や事業計画書づくりは今でも大きな財産となっています。もちろん、当時の仲間たちとの繋がりも。
スポーツマネジメントの世界で学んだことを教室という空間に置き換えることで学級担任の仕事にも変化が現れ、以前より格段に子どもたち一人ひとりを観察する力が起動するようになりました。
それまでは何となくセンサーで子どもたちを導こうしていたわけですから差は歴然です。
なかなか良い感じだと思いつつ、さらに視野を広げたいと思い、何を血迷ったのか仕事を辞めて早稲田大学大学院スポーツ科学研究科へ進学します。
合格が認められた後、社会人大学院なのに県教委の規定に合わず辞めなければ学べないという状況であることが判明。
尽力してくれた関係者の皆様には心配をかけてしまいましたが、「まあいいか!」ということで思い切って辞職しての進学となりました。
ひたすら「なぜするのか?」「具体的に何をするのか?」「それがどのように人々を幸せにするのか?」を問われる日々。
さらには「あなたがやりたいことではなくて、人々が求めていることは何?」と徹底的に問い詰められるようなジリジリとした毎日は何とも刺激的でした。
Jリーグクラブなどプロスポーツチームとまちづくりなどスポーツ政策という現場に立ち会えたことが、後の教室づくりや新たな学校づくりへと繋がっていくことになります。
大きなストレスもありながら「そこにいる人たちが幸せになれる環境設定とは何か?」と考えるツールを与えられた貴重な体験をさせてもらったなと思います。
そこから教室の姿もガラリと変わることになったのです。
リーダーとしての立ち位置は?
先生やコーチ、いわゆる組織のリーダーの姿勢は子どもたちや選手など、そこにいる構成メンバーに大きな影響を与えます。いわゆる権力を振りかざし、常にメンバーを威圧するようなリーダーは今でも多く存在するのではないでしょうか。
子どもの頃から「あれやれ!これやれ!こうしろ!」というような威圧的な先生は大嫌いでしたが、小学校4年生の秋に事件が起きました。
体育の時間が終わってから教室に戻してもらえず、校庭のど真ん中に正座をさせられ、先生からビンタされながら長い説教を受けたのです。
当時のボクはケンカも強く、先輩たちや先生にも遠慮なく意見するような生意気な小学生でした。そんなこともあってクラスではジャイアンのように君臨していたのです。
この校庭の事件後、それまで一緒に遊んでいたクラスメイトもボクを避けるようになり、ボクの行動は常に監視されるようになりました。先生から睨まれ、仲間からも睨まれたように感じたボクは、それまでの自分を封印せざるを得なくなり、人の目を気にする日々を送ることになります。誰にも嫌われないようにと…
この時期の心理状態はトラウマとして今でも残っているなと強く感じる瞬間があります。
「そうだ!あれやってみよう!」とチャレンジをしてみる直前に、「でも、みんなに笑われたらイヤだな」と思ってしまうのは、あの日の記憶が鮮明に蘇ってしまうからだなと分析しています。笑われたとしても誰も責任の取ってくれないのだから関係ないはずなのに…
子どもの頃にみんなから嫌われるというのは何ともいえない深い傷として残るものです。
もちろん、ボクにも落ち度があったことは認めますが、それを助長するのが先生という存在でもあったわけです。どんな組織であってもリーダーの顔色を気にしながら、その空間にいることは辛いことです。先生に認められない友だちとの距離も遠くなるような恐怖感から、「自分さえ我慢すれば良いのであればそうしよう」と自分らしさが失われていくことにもなりました。
それでも…
ボクを支えてくれた多くの先生や友だちに支えながら「自分は自分でいていいのだ!」と思えるようになりました。
「最後は自分の判断でプレーを選択するんだぞ!」
サッカーの恩師、バレーボールの恩師が口を揃えて教えてくれたことです。余計なことは教えずにボクらが自らプレーを選択できるような絶妙な塩梅で場をつくってくれていた先生たちに出会えたことは大きな財産だったと思っています。
「いちいちベンチを見るな!誰のためにプレーしてんのか分からなくなるだろ!オレら指導者の為に君らのプレーがあるんじゃないぞ!」
選手一人ひとりが自分らしく全力でプレーすることを大切にする。主役はそれぞれの子どもたちであり、選手たちで、指導者ではないということです。
そんなことを教えてもらったのだと今でも感謝しています。
続く…
いわゆる普通のプロフィール
桑原 昌之(くわはら まさゆき)
1967年 会津生まれ世田谷・秦野育ち
秦野市立大根小学校・大根中学校・県立秦野高校卒業
東京学芸大学教育学部卒業・早稲田大学スポーツ科学研究科修了
小学校教諭、指導主事など公立の現場から大日向小学校の創設に関わり初代校長を務めた。
現在は、一人ひとりの物語を大切にした学級経営や地域と共につくる学校経営に関する講演や研修も行う教育研究家。
また、JFA公認C級コーチとしてサッカーの指導、JFA Sports Manager(Grade3)などクラブマネジメント、早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘研究員としてもスポーツ政策研究にも関わってきた。
現在の主な活動フィールド –
【スポーツ】
秦野市サッカー協会顧問
伊勢原FCフォレストクラブマネージャー
【教育】
早稲田大学教師教育研究所招聘研究員
関西国際学園顧問・さくらインターナショナルスクール初等部キャリアガイダンスセンター長
フォレスト大楽講師
ボトムアップキャンバスファシリテーター
しつもんメンタルワークブックトレーナー
【まちづくり】
秦野市議会議員
学びの多様化地方議員連盟副会長
Vision
人生という名のボールは転がり続ける。
Mission
挑戦を楽しみ、互いを尊重し、笑顔あふれるコミュニティをつくります。
Value
Challenge
– 新しいことに挑戦し、常に成長し続ける。
Respect
– ありとあらゆるものに感謝し、一人ひとりの物語を大切にする。
Smile
– 出会った人たちを大切に、笑顔のコミュニティをつくる。
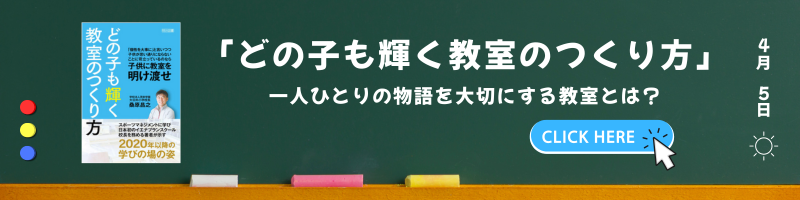
【メディア】
お問い合わせ
講演・ワークショップ・執筆等に関するお問い合わせはこちらからどうぞ。


