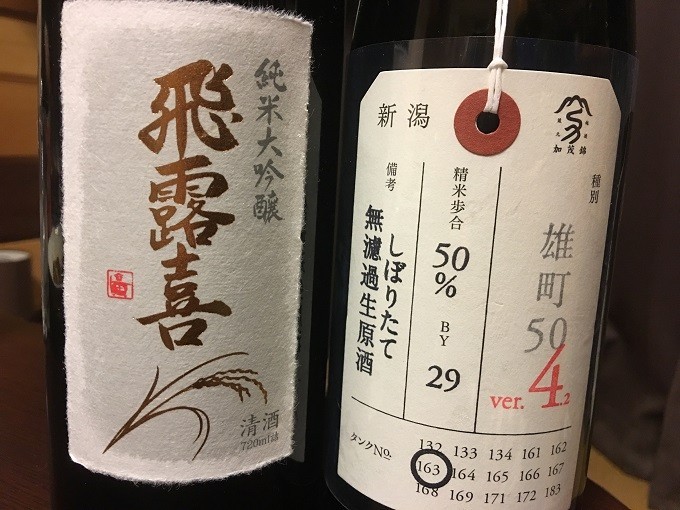
日本酒が好きです。
それも、こだわりをもっている蔵で醸造された酒がお気に入り…
研鑽を積み進化を続けている蔵の酒をありがたく飲む。
杜氏さんたちが、「毎年、同じ酒は造ることができない」ことを知っている。
そんな酒が大好きなのです。
そもそも原料は「米」
その土地の気候にあった酒米が栽培されています。
土や水にもこだわって「米」という素材を最大限に活かして酒造りが行われます。
ベストな土や水なんて、なかなかないのだと思いますが…
それでも…
「どうすれば最良なのか」を必死に考える。
仕込みが始まると、日々、酒蔵の状況を見つめ続けて酒造りをします。
ちょっとした変化も見逃さず、素材本来の力が発揮される手立てを講じる。
これって教育の世界でも大切なことです。
酒造りでは「米」の持つ本来の力を引き出す。
教育では「子どもたち」の持つ本来の潜在能力を引き出すこと。
大量生産できるような一般的な日本酒と呼ばれる清酒があります。
これらは、残念ながら「米」本来の力が出ている酒ではありません。
教育の世界も子どもたちに「同じ基準」を求めてしまうようなところがあります。
本来の個人の姿よりも、みんなと同じように行動できることが求められる。
同じような酒を大量生産できるように、同じような子どもたちを大量に生み出す教室。
上下関係が生まれ、言うことばかりを聞いて過ごす、とても息苦しい世界です。
そろそろ、日本酒業界と同様に変革の時期がやってきたようです。
「子どもたち一人ひとりが最高の旨味を発揮できるような環境」を提供したいものです。
Challenge! Respect! Smile!


