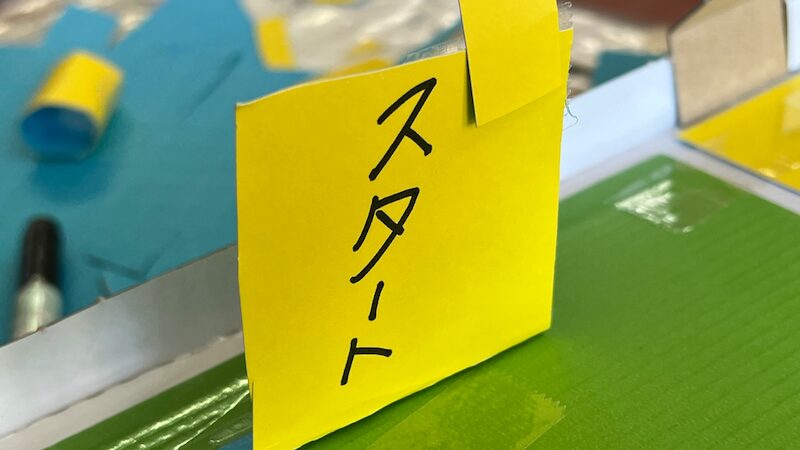全国各地の学校は春休みに入りましたね。
先生たちはホッと一息つきながらも新学期が気になっているのではないでしょうか。
異動がある先生たちは、年度末事務と共に荷物整理も大変かと思います。
ボクも指導要録や教室の整理整頓、新年度の学級編成などに追われたものです。
春休みは夏休みや冬休みとは全く違うバタバタ感がありますよね。
教室を片付けながら一年を振り返る
あらかた子どもたちと綺麗に片付けていても、よくよく見ればやることはたくさん。
使用した教科書や教具の確認、掃除用具のチェック、ロッカーや棚の整理。
掲示物を剥がして、画鋲の芯が残っていればペンチで抜いておく。
いろいろありますよね。
作業をしながら一年を振り返る貴重な時間でもあります。
どんなに頑張っても「ああすればよかったなあ!」は残るもの。
完璧なんてないんです。
「できたことベスト3」は何でしょう?
「もっとこうすればよかった」は一つだけ残してみましょう。
教室が片付くと新年度のことが気になる
教室が片付く頃には少しずつ新年度が気になり始めます。
4月になれば新たな学級の担任となり慌ただしい。
複数学級の学校であれば学年団の先生たちとの新たなチームづくりが必要です。
担任するクラスの子どもたちの名簿や引き続き事項を眺めて期待と不安が入り交じる。
「あの子、どうすればいいかなあ。うまく関係が気づけるだろうか?」
そんな不安に苛まれることは毎年のことでした。
そうやって考え続けることも教師冥利に尽きるわけですが…
とにかくバタバタとしながら入学式・始業式を迎えることにるんですよね。
学級経営の方法よりも大切なことがあった
まだまだ教師として駆け出しだった頃は、教育雑誌や書籍にばかり頼っていました。
「児童生徒指導ガイド」「○学年の学級経営」「学級開きのアクティビティ」など…
いわゆるメソッド本を読み漁っては実践してみる。
そんなことを繰り返しながら数々の失敗を重ね続けては少しずつアップデートされていったのですが…
30代後半から40代前半で教育委員会へ出向、先生たちの研修・研究を支援。
そこでも先生たちにオススメの教育雑誌と書籍を用意する仕事もありました。
当初は自身をもって即実践に繋がりそうな本を多く選んでいたのですが少しずつ違和感が出てきました。
「なんだかパッチワークのようにコロコロやり方を変えても上手くいかないんだよなあ」と。
目指したい教室像の先にあるもの
いろんなメソッド本を読んで、あれこれとアレンジしても結局は上手くはいきませんでした。
「なんで上手くいかないのかなあ?教師として力不足なんだろうか?」
先輩たちのようにはうまくいかない自分の学級経営に不安は増すばかりでした。
そんな時のこと…
「お前な、やり方ばっかり変えたって、そもそもの部分がなかったら上手くなんていかないだろ」
居酒屋のカウンターで先輩がとうとうと語り出しました。
「やり方」よりも「あり方」が大切なんだ!
「例えばよ、フィジカルを高めることなく、姑息なスキルだけで戦って限界あるじゃんね」
先輩との共通言語はスポーツでしたから、これはストンと落ちたのでした。
「 “やり方”も大切だけれど、子どもたちと一緒につくりたい世界観をみつけて”あり方”を考えるんだよ!」
ってことなんですね。
それから、毎年毎年、多くの子どもたちや先生たちと共に過ごしながらアップデートされていく。
やがては…
「ボクがつくる教室」から「子どもたちと一緒につくる教室」へと転換を果たすことができたのです。
教室を子どもたちに明け渡せ!
ご縁をいただき、今から5年前「どの子も輝く教室のつくり方」(明治図書)を出版する機会を得ました。
今でも関係者の皆様には感謝しかない単著です。
正直に申し上げると「パッと読んで成果を上げたい先生」には向かない本です。
どちらかといえば、「自らと向き合い続け、教育とは何かを問い続けている先生」に向いています。
もちろん、哲学書でもありませんが…
「教師としてのあり方」「自分らしく生きるための考え方」「コミュニティデザイン」に触れています。
学級経営に正解なんてないから
世の中には何が正解かなんて分からないことが星の数ほどあります。
そして…
学級経営にも正解なんてありません。
皆さんがチャレンジしていること自体が全て正解なんです。
そこでエラーに気づいて修正を続ければいいんです。
たまたまSNSを通じて本記事を目にした皆さんは、学校の先生、保護者、スポーツ指導者でしょうか。
最後まで読んでくださって本当にありがとうございます。
御礼をかねて書籍を紹介しておきますので、あなたの脳がパカッと開くきっかけになったら幸いです。