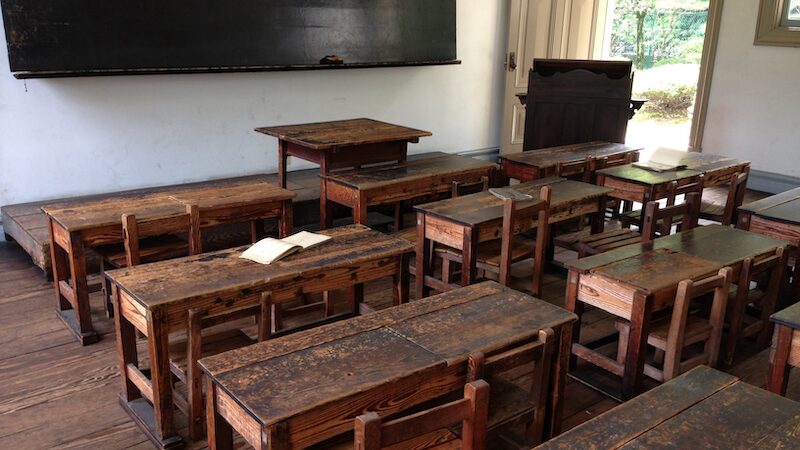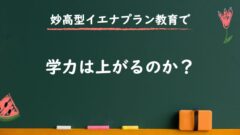第二次世界大戦前、日本が大正デモクラシーの自由教育運動に沸いていた時期、米国の教育法である「ドルトン・プラン」が導入されました。このプランは、個々の自主性や創造性を重んじるものであり、意外にも当時の大日本帝国海軍兵学校(海軍士官学校)において、短期間ながら採用された歴史があります。
その背景と経緯について、以下にまとめます。
ドルトン・プランとは
ドルトン・プランは、米国の教育家ヘレン・パーカーストによって考案された教育法です。以下の2つの原理を基本としています。
- 自由の原理: 生徒一人ひとりの興味や関心、学習ペースを尊重し、自主性と創造性を育む個別学習を重視します。
- 協同の原理: 学校を一つのコミュニティ(社会)と捉え、生徒同士や他学年との交流を通じて、社会性や協調性を身につけさせます。
日本では、大正自由教育運動が最盛期を迎えた大正11年(1922年)に紹介され、成城学園(当時は成城小学校・中学校)などが先進的に導入しました。
海軍兵学校における導入の背景と経緯
海軍兵学校という、厳格な規律を重んじるイメージの強い組織が、なぜ「自由」を重んじるドルトン・プランを採用したのか、その背景には当時の校長の強い信念がありました。
導入者と時期
- 導入者: 永野 修身(ながの おさみ)海軍中将(当時。後の元帥海軍大将)
- 時期: 永野が海軍兵学校長に着任した後の昭和4年(1929年)4月(第60期生入校時)
採用の背景と目的:エリート教育の追求
永野修身は、過去に米国大使館付武官として駐在していた経験があり、その際に米国で注目されていたドルトン・プランに触れ、その教育法に新たな可能性を見出していました。
永野が兵学校長としてドルトン・プラン導入に踏み切った真意は、従来の画一的な詰め込み教育ではなく、「自啓自発」(自ら啓発し、自ら行動を起こすこと)を促すことにありました。
彼の目的は、単なる自由教育ではなく、ドルトン・プランの手法を用いて**「海軍の将来を担うリーダーたるべき、少数の優秀な人材(エリート)の才能と資質を自由に伸ばす」ための秀才教育(英才教育)**にありました。
教科書通りの戦術しか取れない画一的な指揮官ではなく、自ら考え、創造性を発揮できる柔軟な発想を持つ指揮官の育成が急務であるという信念があったとされています。
海軍兵学校での具体的な実施内容
永野校長の号令の下、海軍兵学校では以下のような改革が実行されました。
- 「自啓自発」と「自学自習」のモットー化従来のように「教えられる」のではなく、「自ら学ぶ」姿勢を徹底させました。
- 「自選時間」の導入授業時間を短縮し、毎日午後に「自選時間」(自学自習の時間)を設けました。この時間に何(どの教科)を学習するかは、生徒各自の自由に任されました。
- 教科書の変更軍事学の教科書において、図解など最低限の情報以外は白紙のページを多く設けました。生徒は自ら調べ、考え、必要な事項をその白紙部分に記入していく方式が取られました。
- 成績評価の変更従来の学科(普通学・軍事学)の点数だけでなく、「訓育点」(人間性やリーダーシップの評価)と「体育点」が成績に加味されるようになりました。
短期間での終焉
戦前の日本、特に軍隊組織においてドルトン・プランが導入された事例は極めて異例であり、永野修身の強いリーダーシップと教育観によって実現した、短期間ながらも特筆すべき教育改革の試みであったと言えます。
しかし、この革新的な教育改革は、当然ながら海軍内部や兵学校の教官たちの間で大きな反響と、少なくない反対意見を生みました。永野校長は信念を持ってこの改革を推進しましたが、その体制は長くは続きませんでした。
昭和5年(1930年)11月、永野校長が兵学校を去る(転任する)と、彼が導入したドルトン・プランに基づく教育システムは実質的に放棄されてしまいました。導入からわずか1年半余りのことでした。
最大の理由は、「自由と個性を重んじる教育法」が、「厳格な規律と画一性」を絶対とする海軍兵学校の組織風土と根本的に相容れなかったこと、そして、唯一の強力な推進者であった永野修身校長が転任してしまったことです。
背景には、以下の3つの深刻な対立がありました。
1. 組織風土(カルチャー)との致命的なミスマッチ
海軍兵学校の教育(通称「江田島精神」)は、上官の命令には絶対服従し、個性を抑えてでも集団としての統一行動を最優先する幹部を養成することを目的としていました。
一方で、ドルトン・プランは「自啓自発」を掲げ、生徒一人ひとりの個性や学習ペースを尊重するものです。この両者は、教育のベクトルが正反対でした。
- 従来の海軍教育: 注入主義(詰め込み教育)、上意下達、画一性、精神主義
- ドルトン・プラン: 自主学習、個性尊重、自発性、合理性
兵学校の多くの教官や海軍上層部から見れば、ドルトン・プランは「自由主義的すぎる」「軟弱である」と映りました。
2. 内部からの根強い反対と批判
永野校長の改革は、トップダウンで強引に進められた側面があります。そのため、現場の教官や海軍内の保守的な幹部からは、強い反発や冷ややかな目で見られていました。
主な批判は以下のようなものでした。
- 「理屈っぽい士官」への嫌悪: ドルトン・プランで学んだ生徒は、自ら考える訓練をしているため、物事の理由を問い、時には上官に対しても意見する傾向がありました。これは、従来の「黙って従う」ことが美徳とされた海軍組織において、「理屈っぽい」「扱いにくい」と非常に評判が悪かったとされています。
- 「秀才教育」への反発: このプランは個々の才能を伸ばす側面が強かったため、「画一的なレベルの幹部を大量に養成する」という兵学校の目的から逸脱していると見なされました。
- 永野校長の「道楽」という認識: 革新的な教育法は、永野校長個人の趣味的な試み(道楽)であると揶揄され、組織全体として本気で取り組むべきものとは見なされていませんでした。
3. 強力な推進者の不在(永野校長の転任)
このように組織風土と対立し、内部に多くの反対派を抱えていたにもかかわらず、この改革が1年半でも続いたのは、ひとえに永野修身校長の絶大な権限とリーダーシップによるものでした。
しかし、昭和5年(1930年)11月、永野校長が海軍軍令部次長として転任(事実上の栄転)し、兵学校を去ると事態は一変します。
組織の「重し」であり唯一の推進者がいなくなったことで、それまで抑えられていた反対派が一気に巻き返しました。後任の校長はドルトン・プランに積極的ではなく、現場の教官たちも進んで旧来の教育法に戻していきました。
旧来の教育法への「揺り戻し」
永野校長の転任後、ドルトン・プランは正式に廃止されるというよりも、なし崩し的に放棄されていきました。
結局のところ、ドルトン・プランという革新的なシステムは、海軍兵学校という強固な伝統と規律を持つ組織の土壌には根付くことができず、永野修身という人物の在任期間中のみに実施された、例外的な「実験」に終わってしまったのです。
【参考文献】海軍兵学校教程へのドルトン・プランの導入と放棄について(防衛研究所)
現代の日本の教育改革への教訓
戦前の海軍兵学校という、最も厳格な規律が求められる組織で「自由と協同」を旨とするドルトン・プランが導入され、そして短期間で放棄された事例は、現代の日本の教育改革に対して非常に示唆に富む教訓を与えてくれます。
単なる「古い軍隊の失敗談」ではなく、現代の学校組織にも通底する普遍的な課題を浮き彫りにしています。
教訓1:組織風土(カルチャー)を変革せずして、手法(システム)の導入は成功しない
海軍兵学校での失敗の最大の要因は、「上意下達・画一性」を是とする組織風土と、「自啓自発・個性尊重」を促すドルトン・プランという教育法が、水と油の関係にあったことです。
永野修身という強力なトップの力で一時的に導入(=「植え付け」)はできても、組織の土壌(カルチャー)がそれを受け入れなかったため、彼が去ると同時に即座に「旧来のやり方」へと揺り戻されました。
現代への教訓:これは、現代の教育現場における「GIGAスクール構想」や「探究学習」「主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)」の導入と酷似しています。
文部科学省からトップダウンで「生徒の主体性を育め」「個別最適化学習を行え」という方針(=ドルトン・プラン的な理念)が示されても、学校現場や教員の意識が従来の「一斉授業・知識注入型」のまま変わらなければ、改革は進みません。
- 形骸化: 端末(PCやタブレット)は導入されたが、使い方は従来の「黒板とノート」のデジタル版に過ぎない。
- 現場の抵抗: 「そのやり方では受験に対応できない」「管理が難しい」「前例がない」といった抵抗感(海軍兵学校の教官たちの反発と同じ構造)が根強く残る。
改革の成功には、手法(システム)の導入と同時に、それを運用する現場の教員たちの意識や学校全体の組織風土(カルチャー)を変革するプロセスが不可欠であることを、この失敗は教えています。
教訓2:「育てたい人材像」と「評価する人材像」のズレを解消せよ
海軍兵学校では、ドルトン・プランによって「自ら考え、意見する(理屈っぽい)士官」が育ち始めました。しかし、それは既存の組織にとって「扱いにくい、従順でない」人材であり、旧来の評価軸ではマイナスでした。
つまり、**「創造的な人材が欲しい」(理想)と言いながら、「従順な人材を評価する」(現実)**という致命的な矛盾があったのです。
現代への教訓:現代の日本も同様のジレンマを抱えています。
- 理想(建前): 学校教育では「主体性」「探究心」「創造性」「多様な意見」を育もうとします。
- 現実(評価): しかし、その先の大学入試や(一部の)就職活動では、依然として「画一的な基準での高得点」「知識の正確な再生能力」「協調性(=異論を唱えないこと)」が高く評価される傾向が残っています。
生徒が「自ら考え、探究する」主体性を発揮した結果、既存の評価(例:内申点やペーパーテストの点数)が下がるのであれば、生徒も教員も改革に本気になれません。
「育てたい人材像」を本気で変えるのであれば、その人材を正しく評価するための「評価軸(=大学入試や社会のあり方)」そのものを見直さなければ、教育現場は「理想」と「現実」の板挟みになり、改革は頓挫します。
教訓3:理念の実現には、現場が実行可能な「リソース」と「仕組み」が必須である
海軍兵学校では、「自選時間(自習時間)」を設けましたが、必修科目が多すぎるなど、既存のカリキュラムが過密なままでは、生徒が自由に探究する時間は物理的に不足していました。理念は立派でも、それを実行する余裕(リソース)がシステムに組み込まれていませんでした。
現代への教訓:これは、現在の教員の多忙化問題と直結します。
「探究」や「個別最適化学習」は、従来の一斉授業よりも遥かに手間がかかります。生徒一人ひとりの進捗を把握し、異なる問いに寄り添い、多様な成果物を評価するには、教員に**圧倒的な時間的・精神的な余裕(リソース)**が必要です。
しかし、多くの現場教員は、授業準備以外の校務や部活動、保護者対応などに追われ、疲弊しています。
余裕のない現場に「もっと手間のかかる理想の教育をやれ」と指示だけしても、それは実行不可能です。
ドルトン・プランのような先進的な教育を定着させるには、教員が「やらされ仕事」ではなく、「やりたい仕事」として取り組めるよう、業務を大幅に削減し、裁量権を与え、理念を実行可能な具体的な「仕組み」として現場に提供することが不可欠です。
まとめ
海軍兵学校のドルトン・プラン導入と放棄の事例は、**「①組織風土」「②評価軸」「③現場のリソース」**という3つの要素が揃わなければ、いかに崇高な教育理念も失敗に終わるという歴史的な教訓を示しています。
現代の教育改革が、永野修身の「1年半の夢」の二の舞にならないためには、この3つの壁を直視し、一つずつ着実に乗り越えていく必要があります。