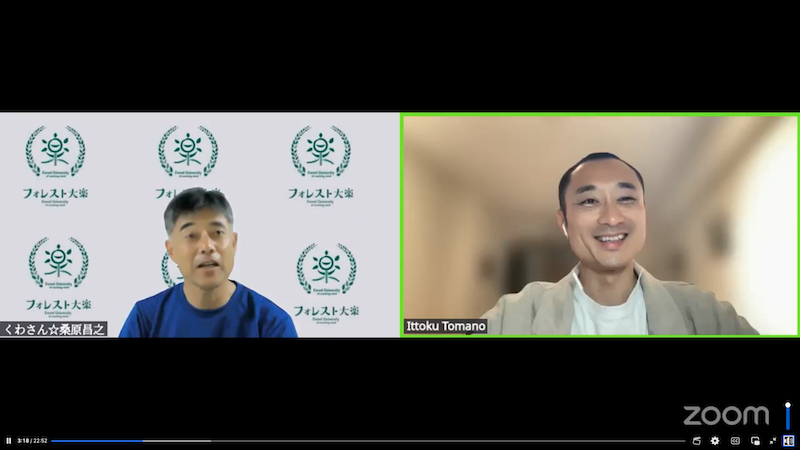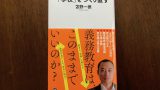今年度に入ってからあらためて「教育の力」について考えています。
「そもそも教育とは?」
30年以上教育の現場にいて振り返ってみると「教育には力があります!」と断言もできる。
でも、その力は、人を元気にすることもあれば、人をダメにすることもある。
あるいは教育そのものが暴力へと繋がるなんてこともあるなあと思っています。
そんなモヤモヤを抱えているタイミングで久しぶりに教育哲学者である苫野一徳先生と対談。
オンラインの学びの場「フォレスト大楽 子育て共育ゼミ」へお越しいただきました。
直接お目にかかったのは2017年の11月。
成瀬小学校の6年生を担任していた教室を参観してもらったことがあるのです。
「その子たち一人がその子らしくいられる空間を、静かな静かな声で、そのまんまを受け入れている教室」
「学びの個別化・協働化・プロジェクト化の融合化の原点」
「見ちゃった、知っちゃった。もう後戻りはできない」
というように当時の教室の空間について語っていただきました。
今年20歳になる子どもたちと丁寧につくった教室のいろんなシーンが蘇ってきました。
あれはいったい何だったんでしょうね(笑)
そんな教室があったおかげで新たな学校をつくるお仕事へ繋がったのでした。
ホントに感謝の言葉しかありません。

フォレスト大楽子育て共育ゼミは冒頭をFacebookライブで中継しています。
今回は冒頭が私と苫野先生、途中からてっちゃん、どんぐりさんにも登場してもらいました。
当日の様子に関するブログ記事はこちら↓
【てっちゃん】https://ifc-forest.com/2531-教育哲学と対話の力/
【どんぐりさん】https://ameblo.jp/univ-semi2012/entry-12904240669.html
AI時代が到来し、小手先のさまざまな教育実践が蔓延する中で必要なのはやっぱり「哲学」でしょうか。
いろいろな話の中で見えてきた学校教育の変革に向けたポイントはこちら↓
「そもそもの対話」×「見ちゃった・知っちゃった」×「応援し合う」教育コミュニティ
これはスポーツの現場でも同じようなことが言えます。
「そもそも私たちは何のために日々のトレーニングを組み立てるのか?」
選手一人ひとりの個性を大切にしながら子どもたちと向き合うクラブの実践を知る。
伊勢原FCフォレストの実践やボトムアップ理論で取り組む国内の学校やクラブからにもヒントがあります。
はたまたビジャレアルのようなクラブもあって海外から学ぶなんてこともできる。
「今は学びの構造転換の過渡期と考えられ、この動きが自治体規模になってきている」
というようなお話もありました。
たしかに学校単位での実践から自治体規模の実践が積み上がっています。
私も共同研究者として参加している新潟県妙高市も市内全体で取り組もうとチャレンジ中です。
いわゆる「見ちゃった・知っちゃった」が積み上がることが大切。
そうした各自治体での実践が繋がると一気に日本の教育も変わるかもしれません。
教育は扱い方を間違えると暴力にもなるけれど、やっぱり人を幸せにするものだと信じています。
今後も多くの実践から学びながら、スポーツと教育の現場、まちづくりへと生かしたいと思います。
当時の様子は「どの子も輝く教室のつくり方」(明治図書)に書いてありますのでご覧ください↓