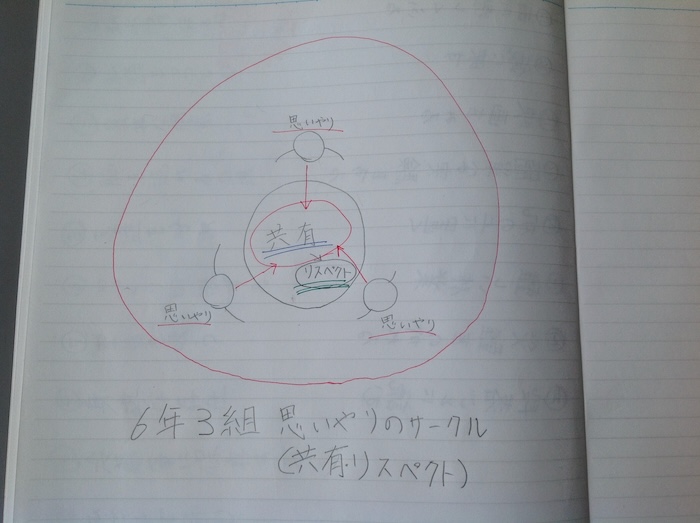「子どもたちの世界が見えるようにするために喋る時間を減らす」
そう言われても喋ってしまうんだ。
「くわまん!話が長いよ!」
子どもたちが笑いながら言う。
そうそう…
担任のボクが主役ではない。
頭では分かっているつもりなんだよなあ。
喋らないことで視覚や聴覚が動き出す。
短く伝えて観察スイッチを入れていく。
そんなトレーニングのような日々が続くうちに少しずつ子どもたちが見えてきた。
ところが見えたら見えたで厄介だった。
「あいつ、あんなことしてるんだな」
「おいおい!今それやる???」
「なかなか良くならないねえ」
子どもたちの「できないこと」ばかりが目についた。
「あのさ、それやめようよ。ちゃんとやろう!」
って注意をすると子どもたちは怒られたような顔をしている。
「こうやればできるよ。やってみな!」
できていないことを指摘して、アドバイスをしてやらせる。
なんだか子どもたちは渋々やっているようにも見える。
どうして子どもたちの「できないこと」ばかりに目が行くのだろうか。
年度の始まりに学級が決まる。
「どんな子に会えるのだろうか?」
まだ知らない子どもたちをイメージしてワクワクするのだが…
配慮の必要な子どもたちについて引き継ぎがある。
それは行動面だったり、健康面だったり、家庭面だったりと多岐に渡る。
まだ経験が浅い頃は、その情報を丸呑みしてしまう。
実際に起きた過去の事実と共に担任だった先生の解釈が入っていることに気づかない。
「じゃあ、あの子は気をつけないといけないな。常時監視だ!」
単純な思考回路で担任として子どもたちと向き合っていた。
「あいつ、やっぱりダメですね」
そんなふうに職員室へ戻っては先生たちと話をしていた。
「でしょー!大変だったのよー!ビシビシやってね」
なんていう激励ともいえない声も飛んでいた。
生粋の体育会育ちである。
そんなことは言い訳にならないが時として怒鳴るなんてこともあった。
一瞬の効果しか残らないのに…
そして、いつも狙っていた。
毎度おなじみの問題を起こす子をマークして見逃すまいと。
子どもたちにとっては完全にイヤなやつだ。
いつも居酒屋であれこれと語ってくれる先輩に質問された。
「お前さ、なんで子どもたちのダメなところばっかり探してんの?」
「えーっと、それを直さないといけないって思うからです」
そんな答えしか持ち合わせていない。
「それホントに直さないといけないの?」
「だって、いろいろやらかすんですよ。あいつ」
「じゃあさ、やらかす原因は何?本人によるもの?」
「???」
全くもって意味が分からない。
担任として間違ったことをしているとは思ってもいない。
ちゃんと指導しているんだし…
「お前な、ちゃんと見てるのか?あいつのこと」
そんなことを言われて逆ギレしそうになった。
「ちょっと見方を変えようぜ。今までのあいつは忘れろ!」
ニヤニヤしながら先輩は言う。
「だからさ、引き継ぎで得た情報に引っ張られすぎなんだよ」
「あいつは○○な子だから気をつけろ!って刷り込まれているだろ」
「いったん、捨てろ。コップを空にして自分で水を入れるんだよ!」
そんなことを伝えて生ビールのおかわりをした。
さらに先輩は語り続ける。
「オレらが子どもたちをみる感覚は、そのまま子どもたちに伝わる」
「お前はあいつを差別的に見ていることに気づいていないんじゃないか?」
「そういうのが他の子どもたちにも伝染してるから壁ができてしまう」
ギョッとした。
子どもたちの世界に壁があるのはボクのせいだと…
人は噂が好きだ。
「あの子、乱暴って聞いているから近寄るのやめなさい」
保護者や先生たちがそう思っていれば子どもたちにも影響してしまう。
子どもたち同士の壁は大人がつくりだしていることもあるのだ。
「じゃあどうすればいいのか?」
ヒントはスポーツの現場にあった。